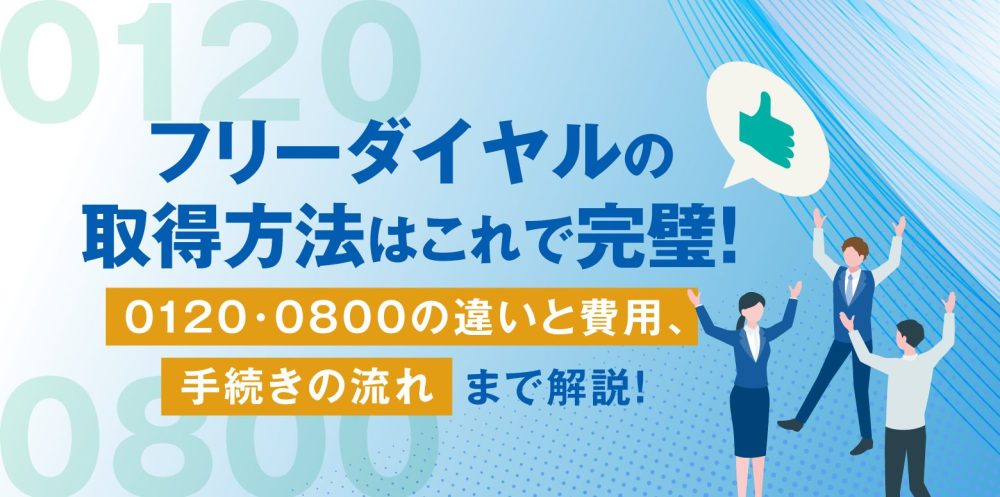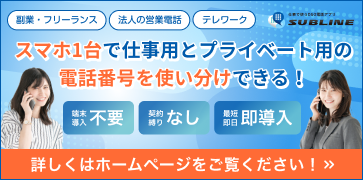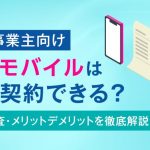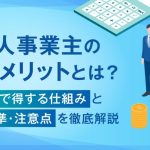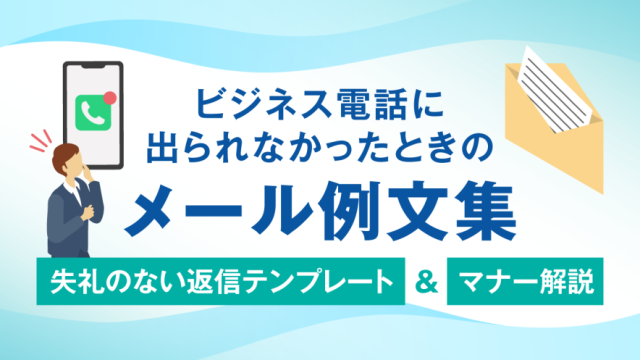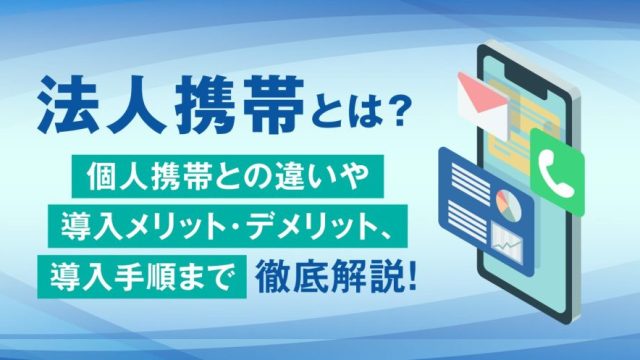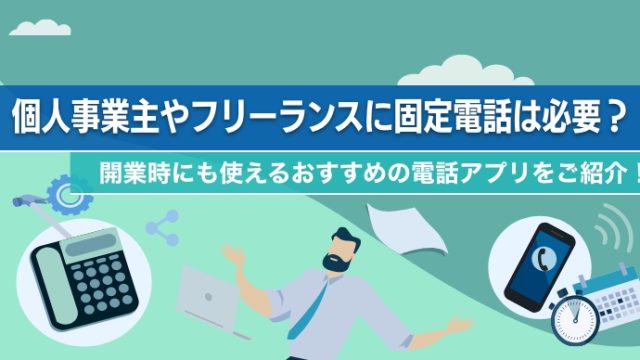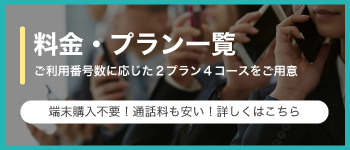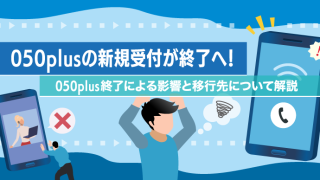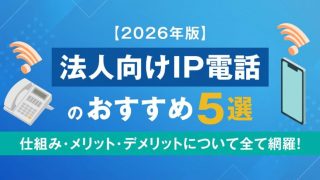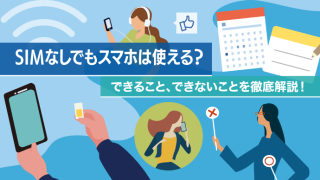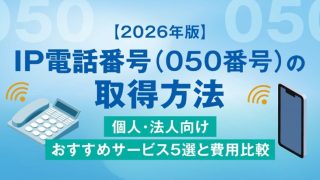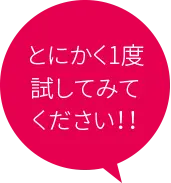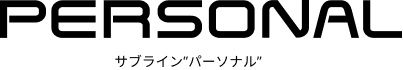本記事では、フリーダイヤル(0120・0800)の取得方法をわかりやすく解説します。
フリーダイヤルとは?仕組みと「0120」「0800」の違い
フリーダイヤルとは、発信者(顧客)の通話料を無料にし、着信者(企業や店舗)がその通話料を負担する「着信課金型電話サービス」です。
顧客が費用を気にせず問い合わせできるため、企業への信頼感を高め、販売促進や顧客満足度の向上に役立つ仕組みとして広く利用されています。
ここでは、フリーダイヤルの基本構造や「0120」「0800」番号帯の違い、利用時の注意点を解説します。
フリーダイヤルの意味と仕組み(着信課金番号とは)
フリーダイヤルは、正式には「着信課金番号サービス」と呼ばれます。発信者が支払うはずの通話料を、着信者である企業側が負担する形で運用されるのが特徴です。
日本国内では主に「0120」または「0800」から始まる番号が該当し、どちらも発信者に料金が発生しません。ただし、一部のIP電話・海外発信・特殊回線などからは利用できない場合もあるため、導入時には対象範囲を確認する必要があります。
また、フリーダイヤルは単独の回線を持つわけではなく、既存の電話(固定回線・IP回線など)にこの番号を“着信課金扱い”として紐付けて利用します。さらに、発信地域ごとに最寄りの拠点やコールセンターへ自動転送する設定(エリア振り分け)も可能で、全国的な問い合わせ対応を効率化できます。
「0120」と「0800」の違いと使い分け方
フリーダイヤルには「0120」と「0800」の2種類があります。どちらも発信者無料の仕組みは同じですが、導入時期や印象、取得しやすさに違いがあります。
| 項目 | 0120番号 | 0800番号 |
| 導入時期 | 1985年にサービス開始。歴史が長い | 1999年に番号枯渇対策として追加導入 |
| 認知度・信頼感 | 高い。「0120=無料窓口」と認識されやすい | 認知度はやや低いが、近年浸透中 |
| 番号の空き状況 | 希望番号の空きが少ない傾向 | 比較的取得しやすく、柔軟に選べる |
| 番号構成 | 「0120+6桁」が一般的 | 「0800+7桁」が主流で、組み合わせが豊富 |
| 主な利用層 | 大企業・金融機関・メーカーなど | 中小企業・個人事業主にも人気 |
通話品質や料金体系は番号帯そのものよりも、契約する通信事業者やプラン内容によって決まるのが実情です。そのため、「0120は信頼性重視」「0800はコスト重視」といった方針で使い分ける企業も増えています。
発信者無料・着信者負担のルールを理解しよう
フリーダイヤルの最大の特徴は、発信者が無料、着信者が通話料を負担すること。この仕組みは顧客への配慮として非常に効果的ですが、運用面ではいくつかの注意点があります。
主な注意点とは?
- 発信できないケースがある
海外・一部のIP電話・特定キャリアなどからは接続できないことがある。 - 通話料は発信元や通話時間で異なる
北海道と九州など、地域別で料金単価が変わる場合がある。長時間通話や遠距離発信ではコストが高くなりやすい。 - いたずら電話や無言通話によるコスト増
無料でかけられる分、意図しない発信が増える傾向がある。 - 管理コスト対策が重要
IVR(自動音声案内)で担当部署を振り分けたり、通話時間制限を設定することで、不要な通話コストを抑えられる。
フリーダイヤルは「顧客への利便性向上」と「企業のコスト負担」が表裏一体の仕組みです。 導入を検討する際は、どの地域・どの時間帯で・どの程度の通話が想定されるかを見極めた上で、最適な番号帯とプランを選ぶことが大切です。
フリーダイヤルを導入するメリット
フリーダイヤルは単なる「無料通話番号」ではなく、企業の信頼性や問い合わせ率を大きく左右する重要なマーケティングツールでもあります。
ここでは、導入によって得られる主なメリットを紹介します。
信頼性・安心感を与えるブランド効果
「0120」「0800」といった番号は、長年にわたり企業の代表窓口として浸透してきたことから、多くの人に“信頼できる企業”という印象を与えます。特にBtoCビジネスでは、問い合わせ先がフリーダイヤルであることが購入前の安心材料になるケースが多く、ブランドイメージの向上にもつながります。
たとえば通販企業や保険会社では、広告やテレビCMにフリーダイヤルを大きく表示することで「サポート体制がしっかりしている」「顧客の声を受け止めている」という印象を作り出しています。中小企業や個人事業でも、代表番号をフリーダイヤルにするだけで問い合わせ率が上がる例は少なくありません。
顧客からの問い合わせハードルを下げる
問い合わせをためらう要因のひとつに「通話料の負担」があります。フリーダイヤルを導入すれば、顧客は無料で電話できるため、気軽に質問・相談がしやすくなります。
特に、見積もり依頼やサポート対応など“電話での最初の一歩”が売上に直結する業種では効果が顕著です。さらに、発信側の通話料を気にしなくて済むため、通話が長くなっても顧客満足度が下がりにくいというメリットもあります。
問い合わせ窓口が増えることで顧客との接点が増え、結果としてリピート率や成約率の向上にもつながります。
マーケティング・広告効果の計測にも活用できる
フリーダイヤルは「どの広告を見て電話したか」を計測するためのマーケティングツールとしても有効です。たとえば、テレビCM・チラシ・Web広告ごとに異なるフリーダイヤル番号を設定しておけば、どの経路からの問い合わせが多いかをデータとして可視化できます。
この仕組みは「トラッキング番号」と呼ばれ、広告の効果測定や改善に役立ちます。また、クラウドPBXやCRMと連携すれば、通話データを自動記録・分析でき、より精密な顧客対応やコスト最適化も可能です。
このように、フリーダイヤルは「顧客対応ツール」であると同時に「マーケティング資産」としても活用できる点が大きな魅力です。
取得前に準備すべき3つのポイント
フリーダイヤルをスムーズに導入するには、申込み前の準備が欠かせません。目的や運用方法を整理しないまま契約すると、想定外のコストや使い勝手の悪さにつながることもあります。
ここでは、導入前に確認しておくべき3つの重要ポイントを紹介します。
利用目的を明確にする(顧客対応/キャンペーン専用など)
まずは「どんな用途で使うのか」を明確にしましょう。フリーダイヤルは、代表番号として常時利用するケースもあれば、キャンペーン・期間限定イベントなどの専用窓口として使うケースもあります。
- 代表番号用途:企業全体の問い合わせ窓口。信頼性と安定性を重視する。
- キャンペーン専用用途:広告効果測定や期間限定プロモーションに活用。トラッキング番号を複数設定することも可能。
- サポート専用用途:既存顧客向け。IVR(自動音声案内)で担当部署に振り分けるケースが多い。
目的を定めておくことで、必要な回線数や転送設定、対応時間などの設計を具体的に決めやすくなります。
着信先回線を確認(固定電話・IP電話・PBX)
フリーダイヤルの着信先となる回線が整備されていなければ、開通手続きが進みません。
主な選択肢は次の3つです。
- 固定電話回線(アナログ・INS)
最も一般的な方法。NTTの回線を利用することで安定性が高く、全国どこからでも発着信が可能。 - IP電話回線(光回線など)
コストを抑えつつ柔軟な転送が可能。特にテレワーク環境や在宅対応に向いている。 - クラウドPBX
クラウド上で電話機能を管理し、スマホやPCで着信できる。複数拠点やリモート対応にも最適。
どの方式を選ぶかによって、必要な機器や費用が変わるため、導入予定の通信環境を事前に確認しておくことが重要です。
法人・個人の区分と必要書類をそろえる
フリーダイヤルの契約には、申込者の属性(法人/個人)に応じて提出書類が異なります。
たとえば、NTTコミュニケーションズでは、以下のような書類が求められます。
- 法人の場合:登記簿謄本、担当者の身分証明書、法人印など
- 個人事業主の場合:開業届の控え、本人確認書類(運転免許証など)
- 代理店経由で申込む場合:委任状や申請書類一式が必要な場合あり
審査の基準は厳しくありませんが、記載内容に不備があると発番が遅れるケースもあります。スムーズに進めるためには、事前に書類を揃え、申込み時に提出できる状態にしておくことが大切です。
フリーダイヤルの取得方法と手順
フリーダイヤル番号を導入するプロセスは、おもったほど難しくありません。ただし、通信事業者の選択から設定・運用開始まで、ステップごとに押さえるべき注意点があります。以下、典型的な流れを順番に見ていきましょう。
通信事業者を選ぶ(NTT・03plus・クラウドPBXなど)
まず、どの事業者(またはサービス)経由でフリーダイヤルを提供してもらうかを決めます。主な選択肢には次が挙げられます。
- ⚫︎NTTコミュニケーションズ(など大手通信会社)
信頼性・安定性が高く、公式なフリーダイヤルサービスとして広く使われています。 - ⚫︎クラウドPBXサービス(例:03plus、IVRy、ナイセンなど)
物理回線を用意しなくても、インターネット回線を使ってフリーダイヤルの着信を受けられることがあります。
03plusは、他社で取得済の着信課金番号(0120/0800)をポータビリティ移行できるオプションも出している。 - ⚫︎その他の通信業者・代理店
中小業者・専門代行業者など、取り扱う番号の種類やサポート体制が異なることがある。
各社で、料金体系・番号の空き・サポート対応範囲・オプション機能(転送、IVR、自動応答など)を比較するのが肝心です。
申し込み方法(Web・電話・代理店経由)
フリーダイヤルの契約申し込みには、主に以下の方法があります。
| 方法 | 特長 |
| Web申し込み | 各事業者のウェブフォームで情報入力。手続きがスムーズで、見積もり取得も簡単な場合が多い。 |
| 電話申し込み | 担当者と相談しながら進めたい場合に有効。条件確認や疑問点の即時解決に向く。 |
| 代理店経由 | 手続き代行や番号選定支援、代理店独自の割引がつくことも。ただし中間マージンを含む可能性もあり。 |
申し込み時には、次のような情報が一般的に求められます。
- ・会社名/事業者名、所在地、法人番号など
- ・担当者名、連絡先
- ・着信先となる電話番号(固定回線、IP回線など)
- ・希望番号(可能なら語呂番号など)
- ・利用目的、想定通話量など
申し込み後は、審査・書類提出・発番手続きへと進みます。
番号の選択と空き番号の確認方法
番号をどう選ぶかは、印象・ブランディング・マーケティング観点でも重要です。
- ●多くの事業者が番号検索システムを用意していて、空き番号をリアルタイムで確認できる。
- ●下4桁や語呂番号の指定をできることがある(ただし必ず希望が通るわけではない)。
- ●人気語呂番号(例:0120-39-xxxx「サンキュー」など)は早めに押さえられることが多く、後から取得困難になる。
- ●希望番号が取れない場合、番号帯を変える(たとえば 0800 にする)という選択肢も検討すべき。
- ●複数番号を発行して、広告媒体別に振り分けてどのルートが反応がいいか測定する企業も増えている。
契約から利用開始までの期間と設定の流れ
申し込み後、発番〜運用開始までの典型的な流れは以下となります。
- 審査・発番処理
申し込み内容、事業者側チェック、番号空き確認などが行われる。 - 開通(設定)作業
番号と着信先電話番号をシステム上で紐づけ、転送設定やルール設定を行う。物理工事が不要なケースも多い。 - 利用開始
開通処理が終わると、フリーダイヤル番号が有効化され、運用可能となる。
期間目安:
- NTT系サービスでは、申し込みから通常5営業日程度で利用可能になることが公表されている。
- クラウドPBX型サービスでは、申込み〜開通まで約12営業日程度を案内している事例もある(例:03plus)。
- 番号移行(ポータビリティ)を伴う場合、さらに日数がかかる可能性あり。
開通後には、次のような設定を行うのが一般的です。
- ・着信先電話番号の設定(どこへ転送するか)
- ・営業時間帯設定/時間外応答設定
- ・自動音声ガイダンス(IVR)振り分け
- ・通話履歴管理・分析設定
- ・無言通話・迷惑電話対策ルール設定
クラウドPBXやWeb管理画面型のサービスを使えば、スマホアプリから転送先を自由に変えたり、全国各拠点・在宅スタッフに配信したりという柔軟運用も可能となります。
フリーダイヤルの費用と料金体系
フリーダイヤルを導入するには、サービス提供事業者・契約形態・運用設定などによってコストが変わります。典型的には初期費用・月額基本料・通話料が主要な構成要素で、オプションや転送方法によって追加費用が発生します。
ここでは、実際の費用イメージとコストを抑えるポイントを整理しておきます。
初期費用・登録料の目安
フリーダイヤル番号を発番・開通する際、下記のような費用が発生することがあります。
| 費用項目 | 目安 | 備考 |
| サービス番号設定工事費 | 約 1,000 円(税抜/番号ごと) | NTTの公式料金表に記載あり |
| 着信先電話番号設定工事費 | 約 1,000 円(税抜/番号ごと) | 同上 |
| 契約回線数に応じた工事・登録料 | 事業者による | 例:NTTでは契約回線数による基本料金選択肢がある |
| 代理店手数料・事務手数料 | 数千円程度 | 事業者・代理店契約による |
また、03plus やクラウドPBX型サービスには「初期費用無料」プランを提供しているケースもあるため、「初期費用ゼロ」を謳うものが全くないわけではありません。
ただし、無料であってもオプションや工事設定に費用がかかる場合があるので、「無料」と記載されていても詳細の確認は必須となります。
月額基本料と通話料(着信者負担構造)
月額基本料の目安
- NTT の「フリーダイヤル基本サービス料金」には、番号ごとに 2,000 円(税抜)プランが公式に示されている。
- また、NTT の申し込み案内では、1回線契約時に 1,000 円、2回線以上契約時に 2,000 円という形を基本料金に設けている記載もある。
- ただし、これはあくまで NTT のプランに基づく例であり、他社やクラウド PBX 事業者はより安いまたは異なる料金体系を採っていることが多い。
通話料(着信側負担)
通話料は発信地域・発信端末(固定・携帯・IP 等)・通話時間・距離(市内・市外・県間)などで変わります。いくつかの例を挙げると
- 固定電話発信 → 例として NTT で市内通話 3 分で約 9.35 円という記載が見られる。
- 携帯電話発信 → 例として、NTT のある比較サイトでは “3 分で 99 円(税込)” としている。
- 一部事業者では、一定距離を超える通話を県外料金扱いにするケースもある。
このため、「全国一律で 8〜20 円/3 分」という表現は、あくまで一例・目安であって、実際には細かく変動することがあります。
また、通話料は、発信者側(顧客)は基本的に無料という仕組みが前提で、“着信者側が課金” となるのが原則です。
注意点:携帯電話発信・制約
- すべてのフリーダイヤル番号が携帯電話からの発信を受けられるわけではないことがある。企業側の設定で携帯発信を制限している例も報告されている。
- どのプランでも、携帯発信の通話料(着信者負担分)は固定発信より高い傾向あり。
スマホ転送・複数拠点利用時の追加コスト
フリーダイヤルを受けた後、スマホや拠点に転送する設定をすると、転送先への通話コストが別途発生する場合があります。
- たとえば、転送先が携帯番号であれば、着信課金 + 転送通話料(事業者設定)という扱いになるケースあり。
- 複数拠点で同時着信させる・負荷分散させるオプションには月額追加料金がかかることも(例:数百~千円台規模)。
- ただし、クラウドPBXを使ってIP通話/インターネット回線経由で転送する方式を取れば、この追加転送コストを抑えられることが多い。多くの解説サイトがこの利点を強調してる。
よくある質問(FAQ)
ここでは、フリーダイヤルの導入を検討する際に多く寄せられる質問をまとめました。
初めて導入する方がつまずきやすいポイントを中心に、実務に即した回答を紹介します。
Q1. 0120番号を取得するにはどうすればいいですか?
0120番号は、NTTコミュニケーションズやクラウドPBX事業者を通じて申し込むことで取得できます。Webからの申し込みが主流で、会社情報・担当者情報・利用目的を入力すると、審査・発番手続きが行われます。希望の下4桁や語呂合わせ番号を指定したい場合は、空き番号検索サービスを活用するとスムーズです。
Q2. フリーダイヤルの開設に必要な書類は何ですか?
申込みの際は、申込者の区分(法人/個人)によって必要書類が異なります。
- 法人の場合:登記簿謄本、担当者の本人確認書類、法人印
- 個人事業主の場合:開業届の控え、本人確認書類(運転免許証など)
代理店経由で申請する場合は、委任状が求められるケースもあります。書類が揃っていれば、最短3〜5営業日で開通可能です。
Q3. 携帯電話から0120にかけると本当に無料ですか?
はい。携帯電話・PHS・公衆電話からの発信も原則無料です。ただし、一部のIP電話(050番号など)や海外キャリア経由の発信は対象外となる場合があります。また、通信環境やアプリ通話(LINE、Skypeなど)では接続されないケースもあるため、注意が必要です。
Q4. 携帯から0120にかけられない場合の原因は?
携帯から0120へ発信できない場合、主な原因は以下の通りです。
- 使用している回線(IP電話・格安SIMなど)がフリーダイヤル非対応
- 企業側のフリーダイヤル契約で「携帯発信を受け付けない」設定になっている
- 一時的な通信障害
この場合、企業側が設定を変更することで受け付け可能にできる場合があります。問い合わせ先に別の電話番号(市外局番付き)を併記しておくと、顧客の取りこぼしを防げます。
Q5. 番号を途中で変更したい場合はどうすればいい?
番号変更は契約事業者に依頼することで可能です。ただし、既存番号をそのまま引き継げる「番号ポータビリティ制度」が利用できるのは、同一事業者内または同系列サービス間に限られます。他社への移行時は新規発番になる場合が多いため、早めの切り替え準備が大切です。
Q6. 個人事業主でもフリーダイヤルを取得できますか?
はい、可能です。03plusやクラウドPBX型サービスでは、法人登記がなくても開業届と本人確認書類を提出すれば申込みができます。小規模ビジネスやネットショップ運営者でも導入しやすく、信頼感アップにもつながります。
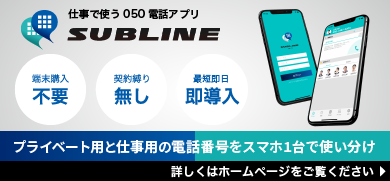

無料でお試しいただけます!
WEBで完結!最短即日で導入完了!
PROFILE
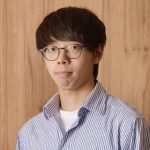
-
株式会社インターパーク/SUBLINEプロジェクトリーダー・マーケティング担当
中途で株式会社インターパークに入社。
仕事で使う050電話アプリSUBLINE-サブライン-のカスタマーサポート担当としてアサイン。
カスタマーサポートを経て、現在は事業計画の立案からマーケティング担当として事業の推進・実行までを担当。
過去、学生時代には2年間の海外留学を経験。