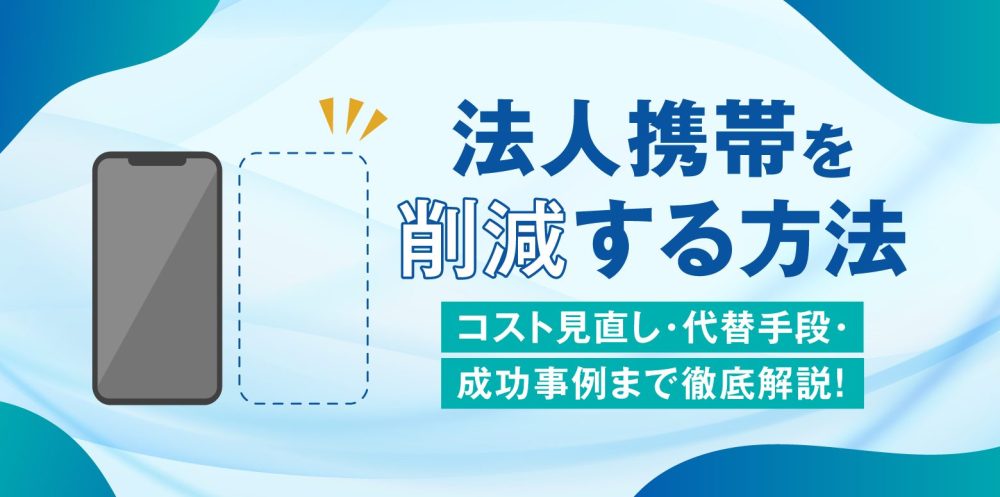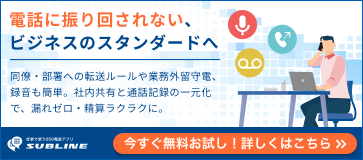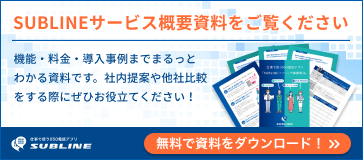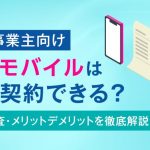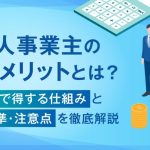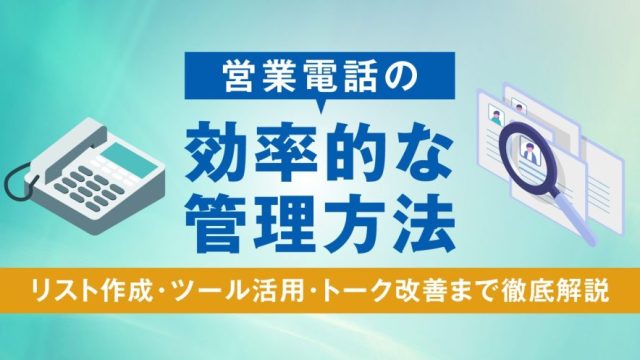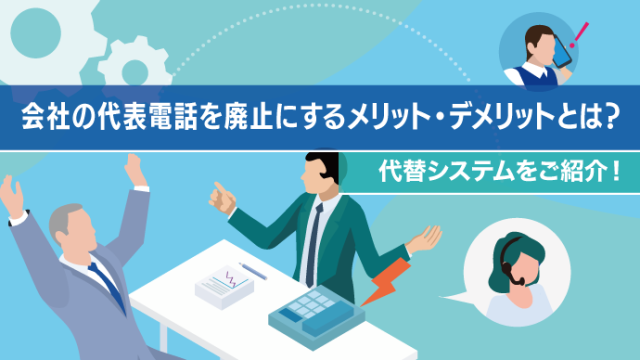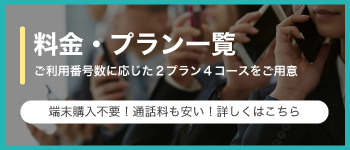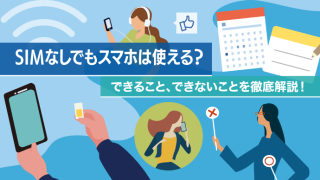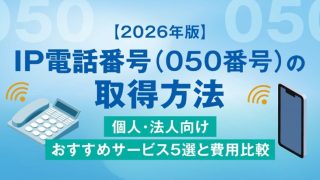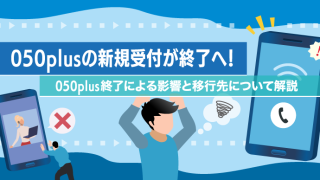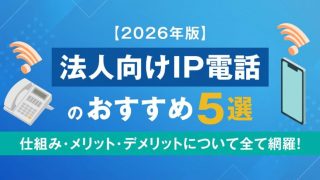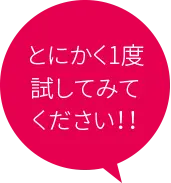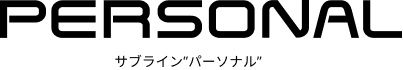本記事では、通信費の見直し、BYODやクラウド電話の活用、代替手段、成功事例を詳しく紹介します。
法人携帯のムダを削減したい、とお悩みの方はぜひご一読ください。
法人携帯の削減が注目される理由とは?
近年、企業におけるコスト意識の高まりや業務の多様化により、「法人携帯の削減」が重要な経営課題のひとつとなっています。これまでは社員1人に1台が当たり前とされていた法人携帯ですが、その保有の必要性やコスト対効果を見直す動きが加速しています。通信技術の進化とクラウドツールの普及により、「携帯を持たずに仕事ができる」環境も実現可能となった今、経営資源を最適化する手段として注目されています。
通信費・端末代の高騰で経費負担が増加
法人携帯の契約には、端末代・月額基本料・通話料・データ通信料など複数のコストが発生します。加えて、キャリアによる値上げや、法人向けの高額なプラン、セキュリティ対策としてのMDM(モバイルデバイス管理)導入など、経費は年々増加傾向にあります。特に社員数の多い企業では、数十台~数百台の契約が積み上がり、年間で数百万円規模の通信費が経営を圧迫する要因となっているのが実情です。
実態に合わない契約台数・利用状況
現場への配布台数は多くても、実際に業務で使われているかどうかは別問題です。たとえば、全社員に配布されているのにほとんど使われていないケースや、数カ月間まったく発着信履歴がない端末も珍しくありません。こうした「実態としては使われていない携帯」が多数存在していれば、見えない損失を垂れ流しているようなものです。実態に合った利用状況の把握と契約台数の見直しは、削減への第一歩です。
DX・テレワーク時代における柔軟な運用ニーズ
働き方改革やDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進、テレワークの拡大によって、「いつでも・どこでも仕事ができる環境づくり」が求められています。これに伴い、従来のように会社から端末を支給するスタイルでは柔軟性に欠ける場合もあります。個人スマホに業務アプリをインストールして使うBYOD(Bring Your Own Device)や、クラウド電話のようなツールを活用することで、法人携帯に依存しない働き方が実現できます。
法人携帯のムダ・見直しポイント
法人携帯は便利な反面、見直しを怠ると不要なコストを生み出す温床になります。配布の目的や使用状況を定期的に精査することで、削減すべきポイントが明確になります。
ここでは、特に見直すべき代表的なムダについて解説します。
通話・データ使用量と契約内容の乖離
契約している通信プランと、実際の使用状況が一致していないケースは非常に多く見られます。たとえば、大容量データプランを契約しているのに、社員はほとんどWi-Fi環境下でしか使っていない、あるいは通話し放題プランにしているがLINE通話や社内チャットで済ませている──といった事例です。このような乖離がある場合、利用状況に合わせたプランへの見直しだけでも大きなコスト削減が可能です。
高額オプションの放置
法人携帯には、契約時に不要なオプションが自動で付帯しているケースが少なくありません。たとえば、留守電サービス、安心パック、キャリアメール、データバックアップサービスなどは、業務に不要であるにもかかわらず、毎月数百円ずつ積み重なり全体で大きな金額になります。すべての端末の契約内容を一度洗い出し、不必要なオプションを削除することで、即効性のある削減が見込めます。
使用頻度の低い端末の見直しと配布適正化
実際に端末が使用されているかどうかを把握できていない企業も多く、数カ月間通話履歴のない“眠った携帯”が存在しているケースもあります。また、部署異動や退職時の回収漏れで“誰も使っていない携帯”が放置されていることもあります。使用頻度の記録を可視化し、必要最低限の配布に見直すことで、台数自体を削減し、契約数・維持費のカットにつながります。
法人携帯を削減する実践策
法人携帯の削減は、単に端末を減らすだけでは成功しません。実態に合った運用方法に切り替えることで、業務効率を損なわずにコストを削減できます。
ここでは、多くの企業が実践している方法をご紹介します。
①契約プランを定期的に見直す
まず取り組むべきは、契約の見直しです。キャリアとの契約内容は一度決めたら放置されがちですが、業務内容や利用状況は常に変化しています。特にデータ通信量や通話頻度が低い社員に対しては、ライトプランへの変更で月額コストを大幅に抑えられます。
また、通信キャリアによっては法人向けの割引プランやボリュームディスカウントもあるため、複数社を比較検討することが重要です。
②BYOD導入による端末費のカットと注意点
BYOD(Bring Your Own Device)とは、社員が自分のスマートフォンを業務でも使用する運用形態です。これにより、企業は端末購入費・維持費を削減できるうえ、社員にとっても使い慣れた端末で業務ができるという利点があります。
ただし、セキュリティや費用負担の取り決めを明確にしておかないと、情報漏えいやトラブルの原因になりかねません。業務用アプリの導入や、通話・データ通信費の精算ルールを整備することが不可欠です。
③クラウド電話・IP電話で“携帯を持たない”選択
物理的な端末を減らす最も効果的な方法のひとつが、クラウド電話やIP電話の導入です。たとえば、スマートフォンにアプリをインストールするだけで業務用番号での発着信が可能になれば、法人携帯を配布する必要がなくなります。
IP電話サービスを活用すれば、個人スマホに業務用番号を付加し、通話内容の録音や転送も柔軟に対応できます。固定電話機や携帯端末からの脱却が、コスト削減と柔軟な働き方の両立を可能にします。
法人携帯の代替に最適なサービスとは?
法人携帯を削減しつつ、ビジネスに必要な通話機能を維持するための有力な手段が「IP電話」です。
IP電話とは、スマートフォンやパソコンにアプリを入れるだけで、会社の固定電話番号を発着信できる仕組みで、物理的な携帯端末やPBX設備が不要になるため、業務のデジタル化とコスト削減の両立が可能になります。
スマホが業務用端末に!050電話アプリSUBLINE(サブライン)とは?

SUBLINE(サブライン)は、お手持ちのスマホにアプリをインストールするだけで、プライベート番号の他にもう一つ、仕事用の050電話番号が持てるサービスです。
個人スマホにアプリを入れるだけなので、端末を新たに支給する必要がありません。なおかつ、社員のプライベート番号を使わずに通話ができるため、BYOD導入時の懸念も解消します。
外出先・テレワークで電話業務がある人、社用携帯を持つのがメンドウな人、社用携帯のコストを削減したい人に最適です。
また、初期費用・月額料金も安価で、導入のハードルが低いのも魅力です。
詳しくは SUBLINE公式サイト をご覧ください。
削減に成功した企業の事例紹介
法人携帯の削減は、多くの企業で実際に成果を上げている取り組みです。
ここでは、業種や規模の異なる成功事例を紹介し、それぞれがどのような手段でコスト削減に成功したのかを具体的に解説します。
【建設業】30台→10台に集約、クラウド電話で外出対応も安心
ある中堅の建設会社では、現場スタッフや管理職に合計30台以上の法人携帯を支給していましたが、実際に利用されていたのは全体の3割程度でした。使用頻度の低い端末を洗い出し、クラウド電話サービスを導入することで、個人スマホでも会社番号での通話が可能になり、携帯の台数を10台まで集約。IVRや転送機能を活用し、オフィスの電話も現場にいる担当者に自動で転送される体制を構築したことで、業務効率は維持したまま通信費を年間約60万円削減しました。
【IT系企業】BYOD導入で通信費60%削減
従業員約50名のIT企業では、従来全員にスマートフォンを支給していましたが、テレワークの普及により利用頻度が低下。BYOD制度を導入し、業務用通話にはクラウド電話サービスを採用。アプリを通じて会社番号を使用し、私用と業務の通話を明確に分離。さらに、通話録音機能によりマネジメントやコンプライアンス面でも安心感を確保できたことで、法人契約の回線は10回線のみに縮小。通信費は60%以上の削減を実現しました。
【営業会社】クラウド電話サービス導入で固定番号の運用コストゼロへ
全国に拠点を持つ営業系企業では、各支店で固定電話番号を維持するためにPBX設備や回線維持費を毎月数十万円支払っていました。そこでクラウド電話サービスを導入。スマートフォンアプリで会社番号の着発信が可能になり、PBXやビジネスフォンをすべて廃止。設備投資と保守費用が不要になり、年間で約240万円のコストカットに成功しました。また、出先からでも本部への内線連絡が可能になり、連携スピードも向上しました。
よくある質問(FAQ)
法人携帯の削減やクラウド電話の導入を検討する中で、多くの方が抱く疑問にお答えします。
制度設計や運用上の不安を解消し、導入をスムーズに進めるための参考にしてください。
BYOD導入時、通話料は誰が負担すべき?
BYODでは、業務利用にかかる通話料やデータ通信料の扱いが重要です。一般的には、会社が一定額を補助する「定額補助型」や、実費精算を行う「実績精算型」があります。
SUBLINEのように通話履歴や録音が残るサービスを使えば、精算処理も明確に行えるため、公平性と透明性を両立できます。
法人携帯を削減してもセキュリティ上大丈夫?
はい、適切なクラウド電話サービスやMDM(モバイルデバイス管理)を活用すれば、セキュリティは十分確保できます。
SUBLINEでは通話ログの記録やデータのクラウド保存、IVRを通じた外部接点の制御も可能なため、法人携帯を持たずとも安心です。
社員の緊急連絡手段として携帯が必要では?
職種や業務内容によっては必要です。たとえば、24時間体制で稼働するインフラ関連や、緊急対応が求められる現場職には、法人携帯の支給を継続すべきケースがあります。
一方で、クラウド電話を導入することで、緊急連絡にも対応できる仕組みを整えることも可能です。
社用携帯の私的利用はどこまで許容される?
会社の方針次第ですが、一般的には「私的利用を最小限に」「長時間の通話やアプリ使用は禁止」といったルールが定められています。業務用端末は会社の資産であるため、利用ポリシーを明文化し、全社員に周知することが重要です。
社用携帯でiPhoneを選ぶ企業はどのくらい?
近年はiPhoneを支給する企業も増えています。特にセキュリティ面や管理性を重視する企業では、iOSの安定性とAppleのMDM対応が評価されています。ただし、端末代が高額になるため、BYODやクラウド電話との併用でコストバランスを取るケースもあります。
法人携帯の主要キャリアのシェアは?
2025年現在、法人向け法人携帯ではNTTドコモ・KDDI(au)・ソフトバンクの3社が主要キャリアを占めています。中でもドコモは安定した通信品質でインフラ系企業に多く、ソフトバンクやKDDIは法人向け割引の柔軟性が評価されがちです。最近では楽天モバイルも法人参入を強化していますが、エリアとサポート体制が導入判断の鍵となります。
社用携帯が必要な具体的な職種とは?
以下のような職種では、法人携帯の支給が依然として有効です。
- 営業職(外出が多く即応性が求められる)
- 建設・設備業(現場と本部の連携)
- 医療・介護職(緊急連絡・オンコール対応)
- 保守・インフラ系(24時間対応・出先連絡)
- マネージャー層(社内外のハブ的役割)
ただし、これらの職種でもクラウド電話で代替可能なケースは増えており、見直しの余地はあります。
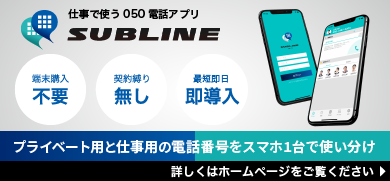

無料でお試しいただけます!
WEBで完結!最短即日で導入完了!
PROFILE
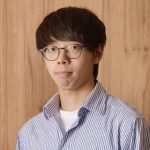
-
株式会社インターパーク/SUBLINEプロジェクトリーダー・マーケティング担当
中途で株式会社インターパークに入社。
仕事で使う050電話アプリSUBLINE-サブライン-のカスタマーサポート担当としてアサイン。
カスタマーサポートを経て、現在は事業計画の立案からマーケティング担当として事業の推進・実行までを担当。
過去、学生時代には2年間の海外留学を経験。