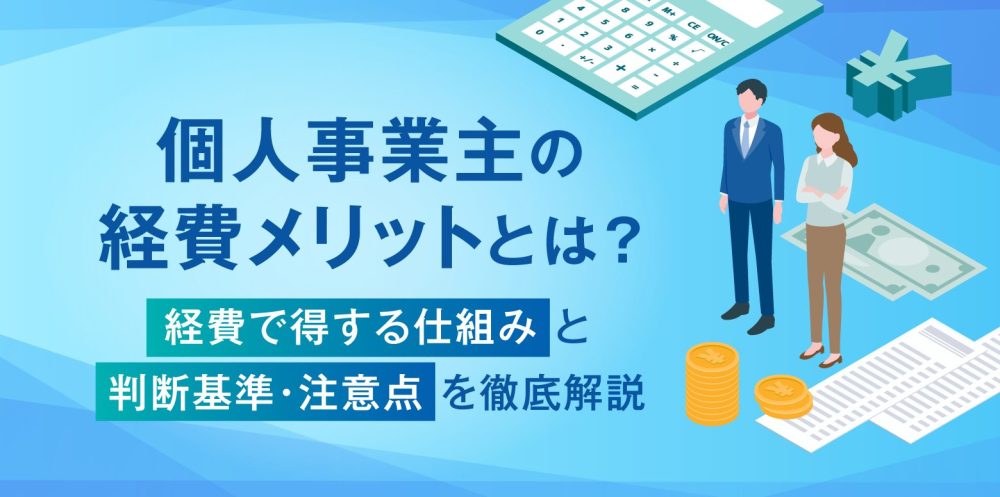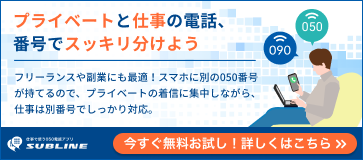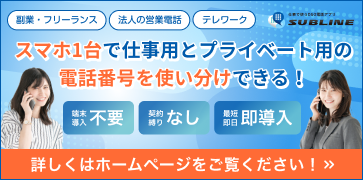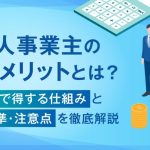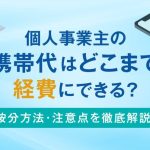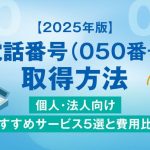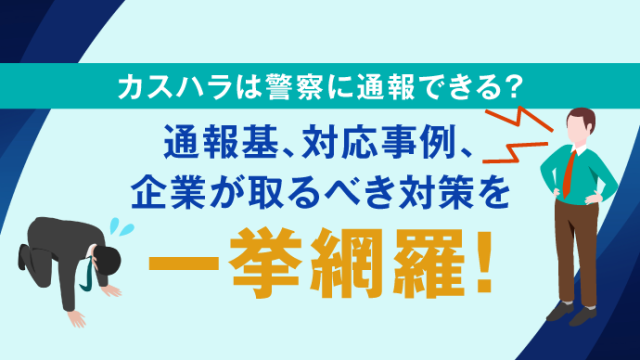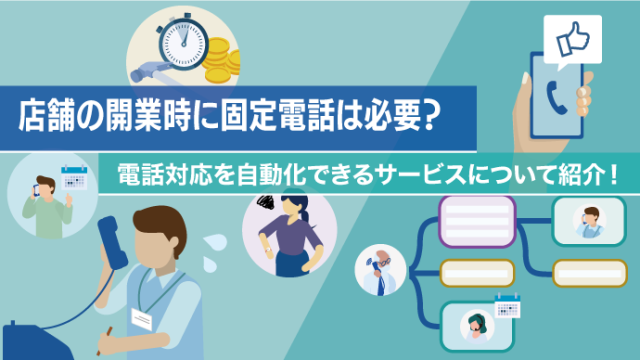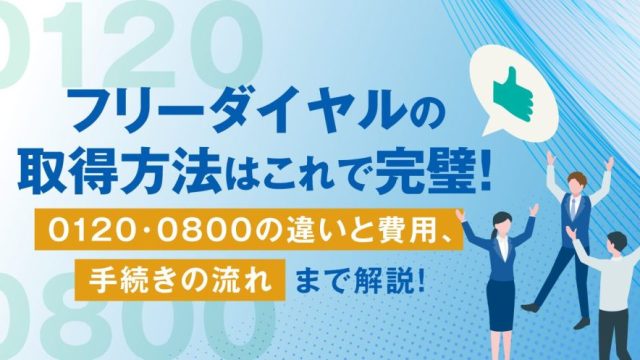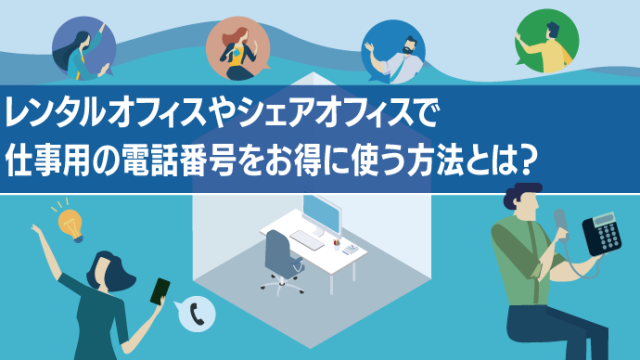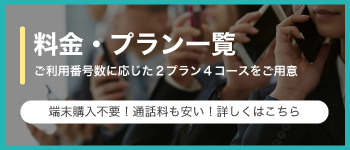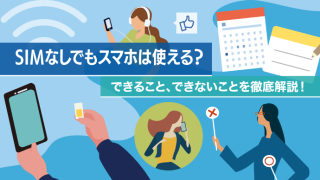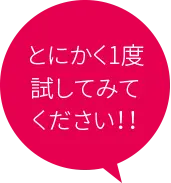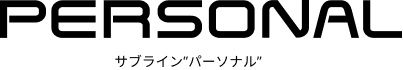個人事業主が経費を計上する最大のメリットは「節税」だけではありません。
本記事では、経費の基本から判断基準、得する使い方、デメリット、注意点まで具体例を交えてわかりやすく解説します。
個人事業主の経費とは?|まずは基本の仕組みを理解しよう
個人事業主にとって「経費」とは、事業を行ううえで欠かせない支出のことです。単なる出費ではなく、「事業のために使ったお金」として税金計算上の所得から差し引けるのが大きな特徴です。経費を正しく理解しておくことは、節税効果を得るうえでの第一歩です。
経費の定義|「事業に必要な支出」とはどんなもの?
経費とは、売上を得るために必要な費用のことを指します。たとえば、パソコンやスマートフォンの購入費、広告宣伝費、交通費、通信費、事務所家賃、接待交際費などが代表的です。
ここで重要なのは、「事業のために使った」と説明できるかどうかです。たとえば、私用の食事は経費になりませんが、取引先との打ち合わせで使ったカフェ代は経費として認められる可能性があります。つまり、「支出目的の説明責任」がポイントになります。
経費で落とせるもの・落とせないものの判断基準
経費になるかどうかを判断するには、「事業との関連性」と「合理的な範囲」がカギとなります。事業との関連性とは、その支出が仕事の遂行や売上の獲得につながっているかがポイントとなり、合理的な範囲とは、支出金額が業務内容や売上規模と見合っているかが判断基準となります。
なので、自宅の家賃や光熱費も、仕事スペースを兼ねていれば一部を経費として按分できます。一方で、家族旅行や日常の買い物のような私的支出は経費にできません。
青色申告・白色申告による経費処理の違い
青色申告と白色申告では、経費の扱い方や控除額が異なります。
- 青色申告:帳簿を正確につける必要がありますが、最大65万円の「青色申告特別控除」を受けられます。また、家族への給与を経費として計上できる「専従者給与」も認められ、節税効果が高いです。
白色申告:帳簿付けが簡単ですが、控除や経費処理の自由度は低めです。
長期的に事業を続けるなら、節税効果の高い青色申告がおすすめです。
経費を計上するメリット|個人事業主が得する理由
経費を計上することは、単に「税金を減らす」だけでなく、事業運営を安定させるための重要な戦略です。正しく経費を把握・活用できる個人事業主ほど、長期的に見て利益を増やしやすくなります。
ここでは、経費を計上する4つの代表的なメリットを解説します。
節税効果|所得税・住民税・事業税が減る仕組み
最大のメリットは、課税所得が減ることで税金が安くなる点です。たとえば年間売上1,000万円、経費が300万円なら、課税対象となるのは残りの700万円。この「経費を増やすほど所得が下がる」構造が節税の基本です。
税率は所得が増えるほど高くなる累進課税なので、経費を正しく計上することで、所得税・住民税・個人事業税の負担を大きく軽減できます。特に青色申告者なら、65万円の特別控除も加わり節税効果がさらに高まります。
キャッシュフローの安定|税金を減らしながら資金を残す
経費計上は「お金を減らすための支出」ではなく、税負担を減らし、手元資金を守る手段でもあります。10万円の備品を購入し、その分課税所得が減れば、結果的に支払う税金も数万円単位で下がります。つまり、同じ支出でも「税金を減らす投資」としての意味を持つのです。
また、適切な経費処理を継続することで、毎月のキャッシュフローを予測しやすくなり、資金繰りの安定にもつながります。
信用力アップ|融資審査で「経営の見える化」ができる
きちんと経費を計上して帳簿を整えると、金融機関からの信頼が高まります。融資審査では「売上」「経費」「利益」のバランスを見られるため、経費処理が曖昧だと経営実態が不明確になり、信用が下がることもあります。
逆に、経費を正確に管理しておけば、利益率や事業の健全性を示す資料として活用でき、資金調達や事業拡大のチャンスを掴みやすくなります。
長期的メリット|設備投資や事業拡大の基盤になる
経費をうまく活用することで、事業の成長基盤を整える投資がしやすくなります。例としては、パソコンや車、広告費などを経費で計上すれば、税負担を抑えつつ業務効率を高められます。これにより、将来的な売上アップや顧客獲得の土台を作れるのです。「今の支出を未来の収益につなげる」、それが経費を戦略的に使う最大の魅力です。
経費を計上するデメリット|注意すべき落とし穴
経費には確かに多くのメリットがありますが、「何でも経費にすれば得」というわけではありません。使い方を間違えると、税金は減っても手元の資金が減り、結果的に事業を圧迫することもあります。
ここでは、経費を計上する際に注意すべき3つの落とし穴を見ていきましょう。
現金が減るだけの「無駄な支出」になるケース
節税を意識するあまり、「税金を減らすための買い物」をしてしまう個人事業主は少なくありません。しかし、10万円使って税金が2万円減っても、実際の出費は8万円残ります。「節税」と「浪費」は紙一重で、事業に必要のない出費はただのマイナスです。
本当に必要なものなのか、「それを買うことで売上や効率が上がるのか」を冷静に見極めることが大切です。
経費を増やしすぎて赤字になるリスク
経費を増やしすぎると、所得が減りすぎて赤字になることがあります。赤字自体は悪いことではなく、翌年以降に繰り越せる「青色申告の赤字控除制度」もありますが、生活費や事業資金の確保が難しくなるリスクもあるため注意が必要です。
特に開業初期は、利益を確保しながら必要最低限の経費で運営する「メリハリ経営」が鍵となります。
グレーゾーン経費は税務署のチェック対象になる
経費として認められるかどうかが曖昧な「グレーゾーン支出」を多く計上すると、税務調査で指摘される可能性があります。たとえば、家族との食事を「接待交際費」として処理したり、私用車を事業用として全額経費にするケースなどです。経費の根拠が説明できない支出は避けること。領収書や取引記録を残し、「誰と」「どんな目的で」使ったかを記録しておけば、調査時にも安心です。
経費計上を成功させるコツ|得するための実践ポイント
経費は「使えば得する」ものではなく、「正しく使えば得になる」ものです。
ここでは、節税効果を最大化しながら、健全な経営につなげるための実践的なポイントを紹介します。
節税効果を最大化するタイミングと使い方
経費を計上するタイミングを意識すると、節税効果がより高まります。たとえば、年末に必要な備品をまとめて購入すると、その年の所得を減らすことができます。逆に、収益が少ない年に大きな支出をしても節税効果は薄くなります。
また、減価償却が必要な高額資産(車、機器、パソコンなど)は、購入時期と償却期間のバランスを考えることが大切です。計画的に支出することで、税金とキャッシュフローの両方を最適化できます。
経費にできる意外な支出(家事按分・通信費・車両費など)
「これは経費にならない」と思い込んでいる支出の中にも、実は経費にできるものがあります。代表的なのが家事按分(かじあんぶん)。自宅兼オフィスで仕事をしている場合、家賃・光熱費・インターネット代などの一部を事業用として計上できます。
また、スマートフォンやパソコン、車の利用も、事業利用割合に応じて経費化できます。ただし、全額を経費にするのではなく、「事業で使った割合」を根拠として明確にすることが重要です。
税理士に頼むべきタイミングと、自分でできる範囲
個人事業の初期段階では、自分で帳簿をつける人も多いですが、売上が増え始めたら税理士のサポートを検討する価値があります。税法は複雑で、経費の判断や節税スキームは年々変化しています。プロに相談することで、無駄な支出を防ぎつつ、法的に安全な節税ができます。
一方で、クラウド会計ソフトを活用すれば、日常の記帳や領収書管理は自分でも十分可能です。「日常管理は自分で」「確定申告は税理士に」など、役割分担を明確にするのが理想です。
経費の見直しで事業の利益率を改善する方法
経費は「減らす」ことでも「利益を増やす」ことができます。毎月の支出を見直し、必要のない固定費(サブスク、通信費、保険など)を削減するだけでも利益率は上がります。
さらに、支出内容を分析して「投資型経費(売上につながる支出)」と「維持型経費(維持するための支出)」を分けると、どこにお金を使うべきかが明確になります。定期的に経費を見直す習慣をつけることで、自然と事業全体の効率が高まります。
経費計上に必要なもの|準備と管理の基本
経費を正しく計上するためには、日々の記録と証拠管理が欠かせません。どんなに正当な支出でも、根拠を残していなければ経費として認められない可能性があります。
ここでは、経費管理をスムーズに行うための基本的な準備を紹介します。
領収書・レシートの保存ルール
経費として認められるためには、支出の証拠を残すことが必要です。具体的には、領収書・レシート・請求書などを7年間保存するのが原則(青色申告の場合)。紙での保管はもちろん、スキャンして電子保存することも可能です。電子帳簿保存法に対応したクラウド会計ソフトを使えば、スマホで撮影したレシートを自動仕訳してくれるため、管理の手間が大幅に減ります。
ポイントは「誰に」「何のために」使ったかを明記しておくこと。メモを添えておくと、後々の確認がスムーズです。
クレジットカード・口座を分ける重要性
プライベートと事業の支出を混同すると、経費処理が複雑になります。そのため、事業用のクレジットカードや銀行口座を別に用意するのが鉄則です。取引が明確になり、会計ソフトとの自動連携もスムーズ。税務調査の際にも「事業で使った支出」を証明しやすくなります。
特に、法人化を視野に入れている場合は、早い段階で口座・カードを分けておくと後々の経理移行がスムーズです。
会計ソフト・クラウドサービスを活用した記帳管理
経費計上の効率化には、クラウド会計ソフトの活用が欠かせません。freeeやマネーフォワード、弥生オンラインなどを利用すれば、銀行口座やクレジットカードの明細を自動で取り込み、経費分類まで自動化できます。
AIによる仕訳提案やレポート機能を使えば、日々の経営状況をリアルタイムで可視化できます。「経理が苦手」な人ほど、ツールの力を借りることで経費管理がストレスなく続けられるようになります。
経費証拠の残し方で税務調査に備える
税務調査では、「その支出が本当に事業に関係しているか」が確認されます。そのため、領収書の保存に加えて、支出の目的・日時・取引相手を明確に記録しておくことが重要です。
たとえば、接待交際費なら「〇月〇日/取引先名/打ち合わせ内容」とメモを添える。交通費なら「移動経路・目的」を残すなど、あとで説明できるようにしておきましょう。また、クラウド上にデータを保存しておくと、紙の紛失リスクも減り、調査時の提出もスムーズです。
よくある質問(FAQ)
経費に関しては、「どこまでがOKなのか」「本当に得になるのか」など、多くの個人事業主が同じような疑問を持っています。
ここでは特によく寄せられる質問をまとめて、わかりやすく答えます。
個人事業主は経費を使ったほうがいいですか?
はい、正しく経費を使えば節税につながります。経費として計上できる支出を漏らさず記録することで、所得が減り、結果的に税負担を軽減できます。ただし、「節税のために無理に支出する」のは本末転倒。事業の成長につながる出費を中心に、バランスよく経費を使うのが理想です。
経費で落とすと何が得になる?
経費で落とす最大のメリットは、税金が減ることです。たとえば、経費が10万円増えると、その分課税所得が10万円下がり、所得税・住民税・事業税がトータルで数万円減ることもあります。つまり、支出の一部を「税金の軽減」という形で取り戻せるのです。
経費で落とすとお金が返ってくる?
正確には「お金が返ってくる」のではなく、支払う税金が減る仕組みです。経費を計上して所得を減らすことで、納税額が少なくなり、結果的に手元に残るお金が増えます。ただし、経費のために現金を使っている点は忘れずに。節税と支出のバランスを意識しましょう。
個人事業主が経費を増やすと赤字になっても大丈夫?
赤字になっても問題はありませんが、生活資金が確保できる範囲でにとどめるべきです。青色申告であれば赤字を最大3年間繰り越せるため、翌年以降の黒字と相殺できます。ただし、赤字が続くと経営の健全性に不安を持たれ、融資が通りにくくなる可能性もあります。
経費の証拠はどのくらい保存しておく必要がありますか?
原則として、7年間の保存義務があります(青色申告の場合)。紙の領収書だけでなく、電子帳簿保存法に対応したクラウドソフトでデータ管理するのも有効です。電子保存を行う場合は、改ざん防止や検索機能などの条件を満たす必要があるため、ツール選びも重要です。
税務署に目をつけられないためのポイントは?
不自然な経費計上を避けることが一番の防御策です。たとえば、「毎月同じ金額の交際費」「家族分の支出を事業経費として処理」などは不自然に見えます。経費処理では、支出の目的を説明できる証拠を残すこと、そして「合理的な範囲」での計上を心がけましょう。
経費処理を簡単にするおすすめツールは?
会計ソフトの活用が最も効率的です。特におすすめは、freee、マネーフォワードクラウド、弥生オンラインの3つ。銀行口座やクレジットカードと連携すれば、自動で仕訳が反映され、確定申告書の作成までスムーズに進められます。スマホアプリでレシートを撮影するだけで経費登録できるのも便利です。
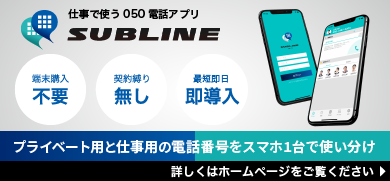

無料でお試しいただけます!
WEBで完結!最短即日で導入完了!
PROFILE
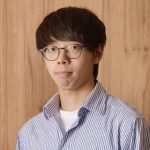
-
株式会社インターパーク/SUBLINEプロジェクトリーダー・マーケティング担当
中途で株式会社インターパークに入社。
仕事で使う050電話アプリSUBLINE-サブライン-のカスタマーサポート担当としてアサイン。
カスタマーサポートを経て、現在は事業計画の立案からマーケティング担当として事業の推進・実行までを担当。
過去、学生時代には2年間の海外留学を経験。